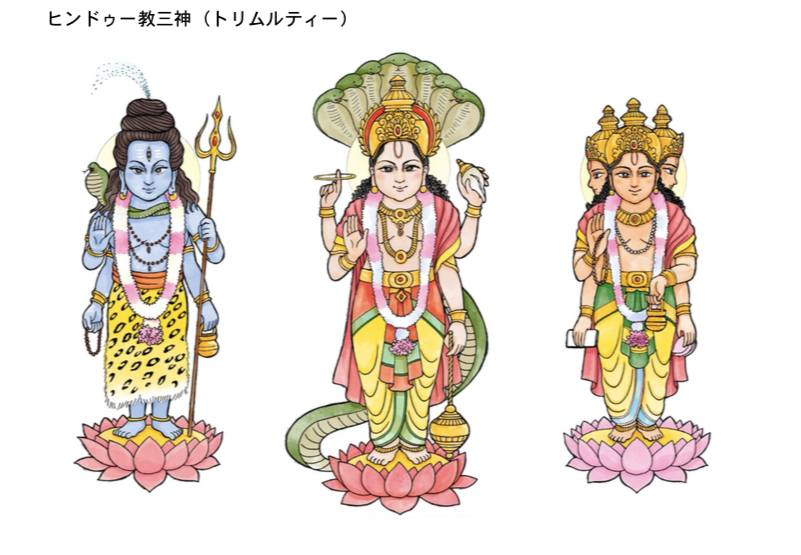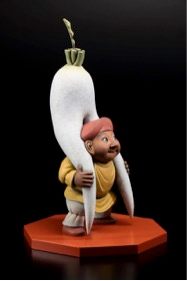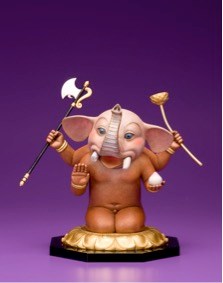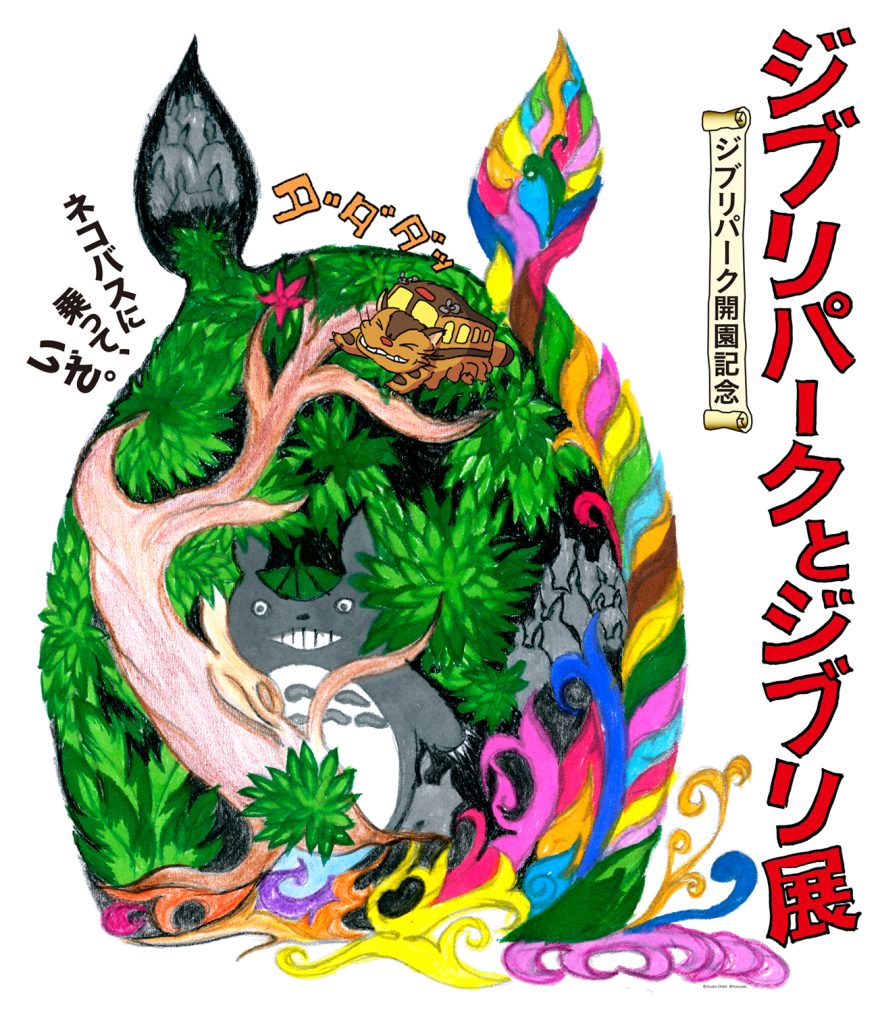本日は鶴田一郎先生のSNSより・・・・・・・・素敵なご報告です。

鶴田一郎先生談
10月30日世界遺産京都醍醐寺におきまして、奉納させて頂きます絵画「醍醐櫻曼荼羅」の入魂式が執り行われました。これから末永く、人々の心に寄り添って行ける絵になってくれればと、心より祈願致しました。
醍醐寺展のご案内です・・・・・
醍醐寺霊宝館秋期特別展
鶴田一郎 −ミューズ達の祈り−
10月15日(土)〜12月4日(日) 午前9時〜午後5時(受付終了は閉門30分前)休館日なし ※行事等の都合により変更の可能性あり会場:醍醐寺 霊宝館京都市伏見区醍醐東大路町22 拝観料金:500円(中学生以上)※三宝院庭園・伽藍は、別途大人1,000円 中高生700円
この度、秋の京都/醍醐寺にて、鶴田一郎の美人画と醍醐寺が所蔵する国宝美人仏画を一堂に展観する、醍醐寺霊宝館秋期特別展を開催いたします。
桜や紅葉の名所としても名高い、世界遺産 総本山醍醐寺の霊宝館に於まして、現代美人画家 鶴田一郎が祈りを込めて描いた美人画・仏画など100点と醍醐寺の寺宝・伝承文化財15万点の中から選りすぐりの美人仏画・仏像を公開いたします。
混沌として、不安の多い情勢の今、鶴田が描く世界の美しさと人々が大切に守り伝えてきた文化財から「人を大切に思う心」を感じていただければと思います。
期間中、本展を記念して講演会やコンサートの開催、ナイトミュージアム、図録・限定グッズの販売なども予定しております。
※イベント等の詳しいご案内は、公式HP または SNS等にて順次お知らせいたします。
感染症拡大により不安な日々が続いておりますが、本展を通して、僅かでも心癒えるひとときをお届けできれば幸いに存じます。
皆様のご来場をお待ちしております。
◆ イベントのご案内 ◆
11月 5日 (土) ワークショップ「醍醐寺令和の寺子屋」 講師:鶴田一郎
※ 近隣の小学校児童招待によるワークショップのため、一般参加は不可。
11月19日 (土) 午後2時〜(約45分間)特別対談「人を大切に思う心」 総本山醍醐寺 執行・統括本部長 仲田順英/日本画家 鶴田一郎
- 11月19日 (土) 午後3時〜(約45分間)♪記念コンサート ヴァイオリン演奏「J.S.バッハ:無伴奏パルティータ第2番」早稲田桜子
◆ ナイトミュージアム ◆
11月 18日 (金) 〜 20日 (日) 午後6時〜午後8時30分
(受付終了は閉門30分前)
- 11月19日 (土) 午後6時 30分〜(約1時間) ナイトミュージアム記念コンサート パンゲア(仲林利恵・仲林光子・十世)
上記 ●印のイベントにつきましては、着席観覧<有料・お土産付>もご用意いたします。
お申し込み・詳しくは 醍醐寺ホームページにて、10/15より受付いたします。
※立ち見席は無料です。何方様もご自由にご覧いただけます。
会場へのアクセス
- 電車でお越しの方
京都市営地下鉄東西線「醍醐」駅下車 ②番出口より徒歩約10 分
- バスご利用の方
京都市バス 301 系統「醍醐寺」下車すぐ
JR山科駅・JR六地蔵駅・京阪六地蔵駅より、京阪バス 22/22A 系統「醍醐寺前」下車すぐ
主催:2022年 醍醐寺鶴田一郎秋期特別展実行委員会、総本山醍醐寺、鶴田一郎事務所
協力:鳳電気土木株式会社、株式会社山本本家
*画像・内容は株式会社鶴田一郎事務所よりお借り致しました。
愛知県,愛知,名古屋市,一宮市,瀬戸市,春日井市,江南市,日進市,清須市,長久手市,愛西市,あま市,半田市,東海市,知多市,岡崎市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,知立市,みよし市,豊橋市,新城市,田原市,名古屋,岐阜県,岐阜市,多治見市,土岐市,美濃加茂市,羽島市,三重県,四日市市,鈴鹿市,亀山市,神奈川県,東京都,東京,銀座,新宿,鎌倉市,高松市,石川県,金沢市,美術,展示会,美術品,絵画,版画,陶器,木彫,ブロンズ,鶴田一郎,ガラス工芸品,買取,高価買取,オークション,原画,委託販売,彫刻,美術品,買取,版画買取,絵画買取,田村和彦,原画価格,鶴田一郎価格,美術館,画廊,鶴田一郎,展示会,artbond,ARTBOND,アートボンド,美人画,現代の琳派,代表取締役田村和彦,KAZUHIKO TAMURA,kazuhiko tamura,名古屋市 田村和彦,名古屋 田村和彦,
#愛知県#愛知#名古屋市#一宮市#瀬戸市#春日井市#江南市#日進市#清須市#長久手市#愛西市#あま市#半田市#東海市#知多市#岡崎市#刈谷市#豊田市#安城市#西尾市#知立市#みよし市#豊橋市#新城市#田原市#名古屋#岐阜県#岐阜市#多治見市#土岐市#美濃加茂市#羽島市#三重県#四日市市#鈴鹿市#亀山市#神奈川県#鎌倉市#東京都#東京#高松市#石川県#金沢市#美術#展示会#美術品#絵画#版画#陶器#木彫#ブロンズ#鶴田一郎#ガラス工芸品#買取#高価買取#オークション#原画#委託販売#彫刻#美術品#買取#版画買取#絵画買取#田村和彦#原画価格#鶴田一郎価格#美術館#画廊#鶴田一郎#展示会#artbond#ARTBOND#アートボンド#美人画#現代の琳派#代表取締役田村和彦#KAZUHIKO TAMURA#kazuhiko tamura#名古屋市田村和彦#名古屋田村和彦#